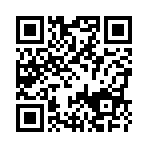› 金武メダリスト › 久々に練習伝達⑦
› 金武メダリスト › 久々に練習伝達⑦2012年11月23日
久々に練習伝達⑦
小中学生の成長(早熟型選手)について
少し長くなりますが、ご父母の皆様最後まで読んでほしいと思います。
先日、石垣島アスリートさんのブログの中で「早熟型の選手」についての問いかけがありました。
以前から私自身この問題には考えさせられ練習に対して少し臆病になったり怖くもなったりでこの問題を避けるようになっていました。しかし他の指導者はどうお考えなのか?とても興味もありました。さすがは石垣島アスリート監督だと思いました。
「早熟型」日本代表クラスを見てみると「小中学生で全国1位になったら」将来オリンピックに出れない様な雰囲気もありますよね。実際にこれまで小中学チャンピオンで日本代表なれたのは男子では400mHの為末さんと100m記録保持者の伊東さんの二人だけでしょうか。特に長距離ではほとんど皆無ですね。
小さく見て地元や地域で見ても「中学校まで速かったのに」高校では伸びなかった。とかいうお話よく聞きます。
しかし、為末さんや伊東さんも早熟型ではないのでしょうか?ならばシニアになってもなぜ活躍できたのでしょうか。おどろく事に為末さんは中学から身長体重がほとんど変わらないと聞きました・・・。 「早熟型とは」いないのか?
たしかに人間ですから成長の早い遅いはあると思います。それを早熟でかたづけてしまっている。早熟という言葉もよくないと本当に思います。
私の関わった生徒の中にも「早熟型」だった、または「早熟型」だ!と周りが決めつけてしまう事がありました。
その子がどんなにその言葉に「絶望感」や「恐怖」を覚えたか?それを思うととても悔しくも悲しくもなります。
ある有名な指導者が「早熟型」への指導方法として、ポイントをふたつ上げています。これを参考にしています。
まず早熟の(と思われる)子は成長が他の子どもより進んでいるわけですから、体格差や体力差で勝ってしまうことが多々あります。この時早熟の子に全く歯が立たなかった子がその後、早熟の子を運動能力で簡単に追い越してしまうことがあります。自分より体力差のある、能力の高い子と運動することで神経系が良く活動し、有効に発達するためといわれています。早熟と思われる子は、身体が大きいことを主に使って勝たせるのではなく、神経系の動作をトレーニングに組み込みながらプランニングをしていかなければなりません。
ですから、絶対に
①体格、体力だけに頼ったトレーニングをしない、させない事。
そして次に
②とにかく子どもの時は陸上競技を楽しんでほしいし、その競技を好きになる事。
よく競技会や練習中に監督コーチから怒鳴られと泣いてうつむいている子を見かけます。この子は将来陸上競技を好きになるだろうか?厳しい指導を否定しているわけではありません。うちのクラブでも叱らなければならないときは叱るようにしています。どこまでが厳しさでというと明確ではありませんが、叱り方にも工夫をすべきです。また、親ばかりが熱心で、子どもはやらされている感が強すぎるのも問題です。と言っています。とても反省でした。怒り方要注意ですね。
結論として「やり過ぎない」特に長距離は注意が必要でしょうか?そして「楽しませる」ことでしょう。
また、成長がある程度止まってしまっても違う練習方法や種目では道は作れます。
また逆に小柄な子は練習より「ごはん食べる!寝る!」「とにかく体を作る」事がもっとも大切かと思います。
そうですね、次回は「栄養学」について書きましょうかね!
大会前は何を食べる?何時間前とか、どんなものは食べない?とか・・・。
また、為末さんの著書やコラムには自身の「早熟型」についての経験や思いその解決方法が語られています。涙が出ます。
興味がある方は読む価値絶対ありですよ。
少し長くなりますが、ご父母の皆様最後まで読んでほしいと思います。
先日、石垣島アスリートさんのブログの中で「早熟型の選手」についての問いかけがありました。
以前から私自身この問題には考えさせられ練習に対して少し臆病になったり怖くもなったりでこの問題を避けるようになっていました。しかし他の指導者はどうお考えなのか?とても興味もありました。さすがは石垣島アスリート監督だと思いました。
「早熟型」日本代表クラスを見てみると「小中学生で全国1位になったら」将来オリンピックに出れない様な雰囲気もありますよね。実際にこれまで小中学チャンピオンで日本代表なれたのは男子では400mHの為末さんと100m記録保持者の伊東さんの二人だけでしょうか。特に長距離ではほとんど皆無ですね。
小さく見て地元や地域で見ても「中学校まで速かったのに」高校では伸びなかった。とかいうお話よく聞きます。
しかし、為末さんや伊東さんも早熟型ではないのでしょうか?ならばシニアになってもなぜ活躍できたのでしょうか。おどろく事に為末さんは中学から身長体重がほとんど変わらないと聞きました・・・。 「早熟型とは」いないのか?
たしかに人間ですから成長の早い遅いはあると思います。それを早熟でかたづけてしまっている。早熟という言葉もよくないと本当に思います。
私の関わった生徒の中にも「早熟型」だった、または「早熟型」だ!と周りが決めつけてしまう事がありました。
その子がどんなにその言葉に「絶望感」や「恐怖」を覚えたか?それを思うととても悔しくも悲しくもなります。
ある有名な指導者が「早熟型」への指導方法として、ポイントをふたつ上げています。これを参考にしています。
まず早熟の(と思われる)子は成長が他の子どもより進んでいるわけですから、体格差や体力差で勝ってしまうことが多々あります。この時早熟の子に全く歯が立たなかった子がその後、早熟の子を運動能力で簡単に追い越してしまうことがあります。自分より体力差のある、能力の高い子と運動することで神経系が良く活動し、有効に発達するためといわれています。早熟と思われる子は、身体が大きいことを主に使って勝たせるのではなく、神経系の動作をトレーニングに組み込みながらプランニングをしていかなければなりません。
ですから、絶対に
①体格、体力だけに頼ったトレーニングをしない、させない事。
そして次に
②とにかく子どもの時は陸上競技を楽しんでほしいし、その競技を好きになる事。
よく競技会や練習中に監督コーチから怒鳴られと泣いてうつむいている子を見かけます。この子は将来陸上競技を好きになるだろうか?厳しい指導を否定しているわけではありません。うちのクラブでも叱らなければならないときは叱るようにしています。どこまでが厳しさでというと明確ではありませんが、叱り方にも工夫をすべきです。また、親ばかりが熱心で、子どもはやらされている感が強すぎるのも問題です。と言っています。とても反省でした。怒り方要注意ですね。
結論として「やり過ぎない」特に長距離は注意が必要でしょうか?そして「楽しませる」ことでしょう。
また、成長がある程度止まってしまっても違う練習方法や種目では道は作れます。
また逆に小柄な子は練習より「ごはん食べる!寝る!」「とにかく体を作る」事がもっとも大切かと思います。
そうですね、次回は「栄養学」について書きましょうかね!
大会前は何を食べる?何時間前とか、どんなものは食べない?とか・・・。
また、為末さんの著書やコラムには自身の「早熟型」についての経験や思いその解決方法が語られています。涙が出ます。
興味がある方は読む価値絶対ありですよ。
Posted by まっぴー at 23:45│Comments(2)
この記事へのコメント
早熟選手については大きな課題がまだ残っていて
実際のところまだまだよくわかっていないというのが日本陸連でも現状のようです。これから色々な研究調査が進むにつれ少しずつよりよい指導方法が考えられていくのでしょう。私たちはその情報をいち早く取り入れ適切な指導をしなければなりませんね。
今年、福地くんが日本一になり先日研修へ行った際に日清カップでの各種目1,2位の子供たちの身体計測を行いました。
これまでのデーターの集計結果X線を使った骨年齢測定でも平均+1歳上の結果が出ていました。貴斗くんは低めの+0.8歳でした。
体格も大きく福地くんでも全参加者のなかで一番小さかったです。
ただ、全国1,2位だけでなく全国大会参加者全体の印象では必ずしも体が大きいとは限らないと感じました。そして、全国大会まで来ると1位〜8位までの差はそれほどありません。
だから1,2位だけに注目しなければまた違った考察もできるのではないでしょうか。
以下私なりの今現在の考え方です。
小中学生が全国大会を目指し、トップの記録を意識し、それに向けた練習をすることは良いことだと思います。決してやりすぎとは考えていません。
ただ、前泊監督の述べるとおり、体格・体力だけに偏ったトレーニンをし、結果にこだわりすぎないことが大切だと思います。
指導者がしっかり学び常に新しい情報にアンテナを張り巡らせ、何が正しく、間違えはどう直せばいいのかを常に考えることです。
子どもは一生懸命練習し、やはり速くなりたい、強くなりたいと考え全力でチャレンジしています。それに答えてあげるためにも指導者は精一杯の頭を使い、体を使い、全力で答えてあげることだと思います。
そうすれば、やりすぎ!という言葉は自然に出てこなくなるのではないか・・・そう考えるようになりました。
まだまだ、本当に沢山勉強することがあります。
情報は共有しあい、子供たちの夢を叶えてあげられるように成長したいですね。
長々と失礼いたしました。
石垣島アスリートクラブ 新谷
実際のところまだまだよくわかっていないというのが日本陸連でも現状のようです。これから色々な研究調査が進むにつれ少しずつよりよい指導方法が考えられていくのでしょう。私たちはその情報をいち早く取り入れ適切な指導をしなければなりませんね。
今年、福地くんが日本一になり先日研修へ行った際に日清カップでの各種目1,2位の子供たちの身体計測を行いました。
これまでのデーターの集計結果X線を使った骨年齢測定でも平均+1歳上の結果が出ていました。貴斗くんは低めの+0.8歳でした。
体格も大きく福地くんでも全参加者のなかで一番小さかったです。
ただ、全国1,2位だけでなく全国大会参加者全体の印象では必ずしも体が大きいとは限らないと感じました。そして、全国大会まで来ると1位〜8位までの差はそれほどありません。
だから1,2位だけに注目しなければまた違った考察もできるのではないでしょうか。
以下私なりの今現在の考え方です。
小中学生が全国大会を目指し、トップの記録を意識し、それに向けた練習をすることは良いことだと思います。決してやりすぎとは考えていません。
ただ、前泊監督の述べるとおり、体格・体力だけに偏ったトレーニンをし、結果にこだわりすぎないことが大切だと思います。
指導者がしっかり学び常に新しい情報にアンテナを張り巡らせ、何が正しく、間違えはどう直せばいいのかを常に考えることです。
子どもは一生懸命練習し、やはり速くなりたい、強くなりたいと考え全力でチャレンジしています。それに答えてあげるためにも指導者は精一杯の頭を使い、体を使い、全力で答えてあげることだと思います。
そうすれば、やりすぎ!という言葉は自然に出てこなくなるのではないか・・・そう考えるようになりました。
まだまだ、本当に沢山勉強することがあります。
情報は共有しあい、子供たちの夢を叶えてあげられるように成長したいですね。
長々と失礼いたしました。
石垣島アスリートクラブ 新谷
Posted by 石垣島アスリートクラブ at 2012年11月24日 16:46
at 2012年11月24日 16:46
 at 2012年11月24日 16:46
at 2012年11月24日 16:46石垣島スリートクラブ新谷監督コメントありがとうございました。
とても勉になりました。やはり結果は大切ですね。自分もやりすぎの言葉をなくせるよう頑張ります。
とても勉になりました。やはり結果は大切ですね。自分もやりすぎの言葉をなくせるよう頑張ります。
Posted by まっぴー at 2012年11月25日 12:03
at 2012年11月25日 12:03
 at 2012年11月25日 12:03
at 2012年11月25日 12:03※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。